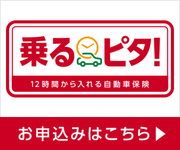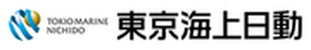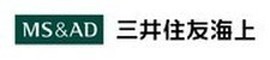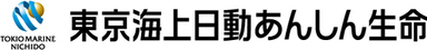2017年5月号
“大雨”による災害に備え対策を!
毎年、全国で甚大な被害/早めの準備、行動が重要
毎年のように大雨による災害が日本各地で発生しています。異常気象が普通になりつつあり、「最近、雨の降り方が変わってきた」と感じる方も多いのではないでしょうか?
日本では、季節の変わり目に前線が停滞し、しばしば大雨を降らせます。初夏から秋にかけては、日本に接近・上陸する台風が多くなります。近年は、短時間に狭い範囲で非常に激しく降る雨、いわゆるゲリラ豪雨も頻発しています。とくに道路が舗装された都市部では、川の急激な増水、道路や住宅の浸水、地下街の水没といった被害も多く、また、雨で増水した川を見に行って流されてしまったり、浸水した道路で側溝の境界が見えにくいために転落したりする事故なども発生しています。
しかも、険しい山や急流が多い日本は、大雨によって、川の氾濫や土石流、がけ崩れ、地すべりなどが発生しやすい自然環境でもあります。
昨年(平成28年)も、6月に梅雨前線が本州付近に停滞し、その前線上を次々と低気圧が通過するなどした影響で、西日本を中心に記録的な大雨となりました。とくに九州地方の広い範囲で猛烈な雨となり、土砂災害、浸水被害が発生し、熊本県で6人が犠牲となり、福岡県では1人が行方不明となっています。西日本から東日本にかけても住家被害のほか、停電、断水、電話の不通などライフラインに被害が生じました。
自然災害から自分や家族の身を守るためにも、大雨になりそうなときは、最新の気象情報を確認し、早めの準備、早めの行動を心がけてください。お年寄りや子どものいる家庭では、避難に時間を要します。また、避難するときも安全なルートを通って移動できるよう、日ごろから、市区町村が作成している「ハザードマップ」などを活用して、危険箇所を確認するようにしましょう。

「食中毒」が発生しやすい季節です
〜食中毒を引き起こす主な原因は「細菌」と「ウイルス」〜
細菌は高温多湿を好む/家庭でもしっかり予防
給食の「きざみのり」についていたノロウイルスが原因で、小学校などで起きた集団食中毒が大きくニュースで取り上げられました。
食中毒は1年中発生していますが、梅雨の時期から夏にかけてはとくに注意が必要となります。食中毒を引き起こす主な原因に「細菌」と「ウイルス」があります。どちらも目には見えない小さなものです。厚生労働省の資料によると、平成28年に全国で発生した食中毒の数は1,140件にのぼります。患者数は20,253人、死者数は14人でした。そのうち細菌が原因だったのが481件、ウイルスが356件となっています。
細菌は温度や湿度などの条件がそろうと食べ物の中で増殖し、その食べ物を食べることにより食中毒を引き起こします。代表的なものとして、腸管出血性大腸菌(O-157、O-111など)やカンピロバクター、サルモネラ属菌などがあり、多くは湿気を好むため、気温が高くなりはじめ、湿度も高くなる梅雨時には、細菌による食中毒が増えます。
一方、ウイルスは低温や乾燥した環境中で長く生存します。細菌のように食べ物の中では増殖しませんが、食べ物を通じて体内に入ると、人の腸管内で増殖し、食中毒を引き起こします。代表的なものにノロウイルスがあります。
こうした細菌やウイルスは、私たちの周りの至るところにいますから、飲食店だけでなく、家庭内でも食中毒は発生します。食中毒を防ぐには、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない(低温で保存)」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける(加熱)」の3つが基本となります。ウイルスの場合は、ごくわずかな汚染によって食中毒を起こしてしまいますから、ウイルスを「持ち込まない」、食品に「つけない」を徹底するようにしてください。
平成28年 原因物質別食中毒発生状況(資料:厚生労働省)

おくだ保険新潟/株式会社奥田新潟
 なんでもお気軽にご相談ください
なんでもお気軽にご相談ください
営業時間:月〜金曜日 9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日休み)
新潟県新潟市中央区米山2-6-2
にいがたe起業館202